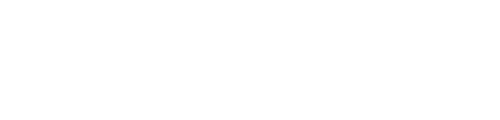2012年3月27日
やっと咲き出した五味ケ谷桜(岸田歯科本院 )河津桜 昨年より1ケ月遅れです。 ホームステイの受け入れ齊藤家としては始めての経験であります。オーストラリアよりヘイディ・レニー・アイセルさん女性3月26日より30日までの鶴ヶ […]
2012年3月24日
杉下小学校中庭のさくら毎年一番早く咲くさくらだ 卒業式の頃に咲く時もある。今年はまだまだ硬いつぼみであった。 つぼみには硬い意思があり、その意思を曲げることは無い、つぼみの考えも簡単に変わるものでもないがその場面を何 […]
2012年3月22日
椿 今年も扁桃腺の炎症で苦しんでいます。 今後、一ヶ月は咳が続きます。 皆様、体に注意をして風邪など引かぬように元気で過ごしてください。
2012年3月20日
シュンラン 寒くとも遅れずに咲いていました。以前は何処の林にも咲いていましたが、今は貴重で高価な野草です。いろいろな色があり、変わった色の花は特に貴重です。 鶴ヶ島市平成24年度第1回定例議会が終了しました。24議案1請 […]
2012年3月16日
ひそかに咲いていたクリスマスローズ白色と紫色が我が家にはあります。寒い中でも大きな花弁を広げていました。最初は下向きにさいてやがて正面を向いて大きく開いています。寒さに強いので育てやすい。 平成24年度の予算と基本方針に […]
2012年3月15日
さんしゅの花が咲きだしました。享保の飢饉 大岡越前がさんしゅの実を薬(強勢剤)にして人口を増し、飢饉で亡くなった人の代わりを育てる為にさんしゅの木を植える事を奨励したとのお話? 富士見中学校第31回卒業証書授与式毎年、感 […]
2012年3月12日
3月11日 新しい芽吹きの始まりの日 忙しく悲しい一日でした。テレビでは朝から深夜まで一年前の映像が流れ一日中、涙 涙 ・・・・・でした。私は意外と涙もろいところがあり、日が変わるまでには小さなさかずき一杯ぐらい出たかも […]
2012年3月10日
梅の花が咲きだした。 我慢しきれずに咲いたという感じ。 植物の感度は素晴らしく自分の成長に合った条件が整う まではじっとして時期を待ちきれいに開花する。 文教厚生常任委員会が行われました。 一般会計において 民生費 […]
2012年3月6日
3月3日 春祈祷五味ケ谷と上広谷中央区による春の年行事今は両地区の往復し祝詞を上げる行事であるが両地区の行事としての参加者は多く各家の跡継ぎが対象者である。 議会が始まり毎日が忙しく、ブログを書く時間が無いです。総務 […]
2012年3月6日
福寿草太陽に向かって開く、夕方には閉じてしまう。寒い冬の終わりに咲き出し、夏には地中に隠れてしまうが土の中でもしっかりと次の寒い冬に耐えるべく根を伸ばしている。 28日に平成24年第1回鶴ヶ島市議会定例会が開会となり初日 […]